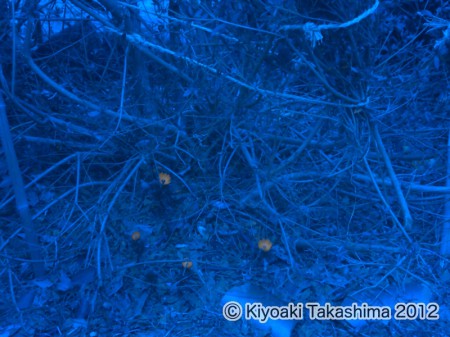ふりだしに戻りました。。。
先日OM-Dに紫外線写真用のフィルターを合わせてフクジュソウを撮影したところ、思わぬ結果のよさに大きく心が動いたのが最初。勢いE-PL1の改造に取り組んで、再び紫外線写真の沼にはまり込んでしまったのですが、数日の格闘の結果、気がついたら最初の時点に戻っていました。

E-PL1での撮影です。前回までのフィルターに、更にもう一枚、手持ちの赤外カットフィルターを足してみました。出てきた結果を見て、これはもう笑うしかありませんでした。カメラのセンサーから外した青いフィルターは、今日レンズの前に追加したケンコー製赤外カットと非常によく似た特性だったようです。色合いも見た目そっくりですし。改造直後にしまったと思ったのは、デフォルトのE-PL1に紫外線写真用フィルターをつけて試し撮りを一切やっていなかったことでした。
そして、この数日の試みでうすうす感じ始めていたこと。何だか赤外写真を見ているようではないか?フィルターから赤外がかなりもれているんじゃないか?実を言うと、昨日海野さんから電話があり、まさにそのような指摘をもらっておりました。
各フィルターの分光特性を見ると、明らかなのは700nm付近に1割ほどの透過率で赤外線を通していて、それ以上の赤外も数%通していることが予想できます。わずかな光量で問題無いと思いたかったけど、そうではなかった・・・
今日のこの結果で、すべてが完全に繋がった感じです。
私がこれまでブログで公開した写真のうち、紫外線写真と呼べるものは、残念な事ですが、どうやら先日のフクジュソウの写真くらいしかなかったようです。でも、これからはいくらか自信を持って紫外線写真と呼べるものを撮影していけそう・・・いやまてまて、本当にそうなのかな?他の二種類の紫外線フィルターと入れ替えたらどうなるのかな?
おお、、なんてこった。
と、まあこんな具合に、これから先も紫外線写真の結果に一喜一憂することが予測されますが、少しずつ進めていきたいと思います。
本日の収穫はもう一つ、ストロボを光源にしても結果が良さそうだったこと。紫外線ストロボはたぶん発光管が紫外線透過率の高いものを使っているのでしょうけど、普通のストロボでもそれなりに紫外線を放出しているようです。今日の紫外線写真は全てストロボを使いました。
川原のヤナギの花。

実際に虫の眼にどう見えているのか分かりませんが、何とも魅力的な輝きを感じます。
ヤナギの通常光での画像

鉢植えのウメ

フキノトウ

庭のまだ花が開いていないものです。花が咲いたときどうなるのか、楽しみです。